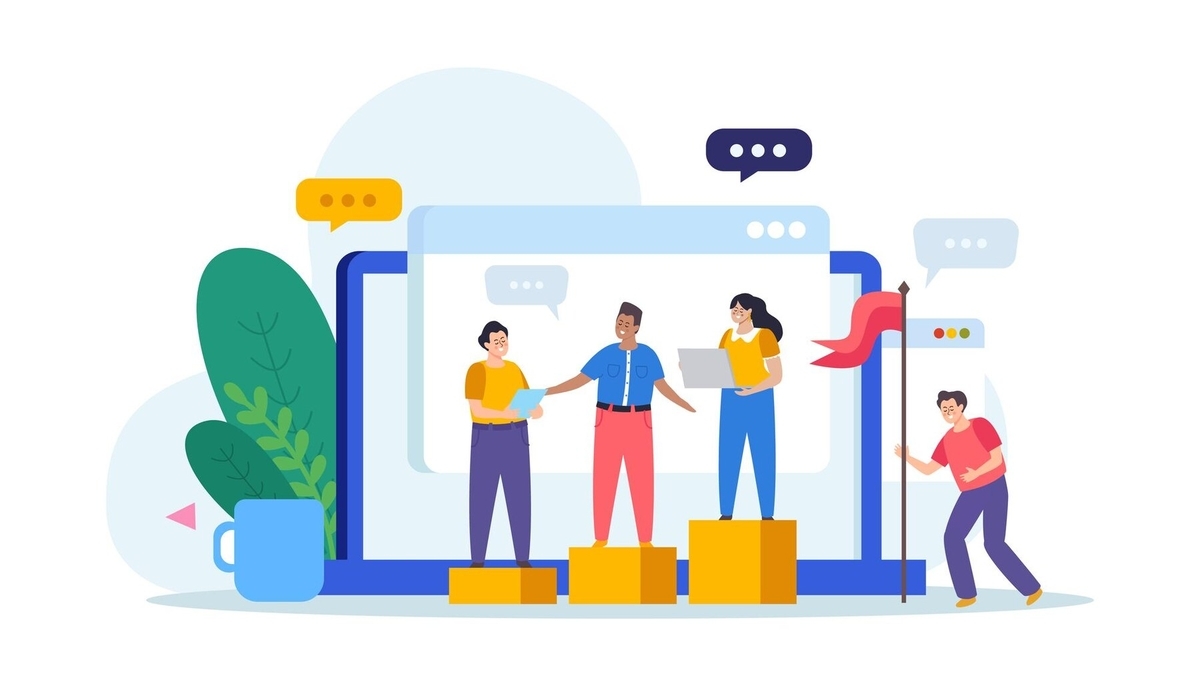
設備がいつ故障するか分からないまま、定期点検や経験に頼っていませんか?
CBM(状態基準保全)は、設備の“状態”を見える化し、最適なタイミングでメンテナンスを行う手法です。
本記事では、CBMの基本概念から、製造業や鉄道業界での実際の導入事例、従来の保全との違いや導入時の課題までを具体的に紹介します。
CBMとは何か? <予防保全の次の一手>
CBM(Condition-Based Maintenance:状態基準保全)とは、機械や設備の実際の“状態”に基づいて保全(メンテナンス)を行う手法です。
従来の定期保全(TBM:Time-Based Maintenance)が「一定時間ごとに保全する」のに対し、CBMは「状態が悪化しはじめたタイミングで保全する」ことが特徴です。
例えば、人間で言えば「半年ごとの健康診断(TBM)」ではなく、「日々の体調チェックをもとに、異変があれば病院に行く(CBM)」という考え方です。
これにより、「まだ使える部品を交換するムダ」や「予期せぬ故障によるダウンタイム」を大きく減らせます。
CBMが注目される背景
IoTやセンサー技術の進化により、設備の温度・振動・電流などをリアルタイムに監視できるようになりました。これがCBM導入の追い風となっています。
単なる“経験と勘”ではなく、データに基づいた保全判断が可能になることで、コスト削減と設備稼働率の向上を両立できるようになったのです。
特に以下のような課題を持つ現場で、CBMは有効です。
・保全費用が高騰している
・定期保全でも故障が多発する
・技術者の経験に依存しすぎている
・設備が古く、状態のばらつきが大きい
CBM導入/活用事例
製造業でのCBM導入事例:ベアリングの異常検知
ある自動車部品メーカーでは、組立ラインで使われるモーターのベアリングにセンサーを取り付け、振動と温度を常時監視しています。
以前は半年ごとに定期交換していたベアリングですが、まだ使用可能な状態でも交換していたため、コストがかさんでいました。さらに、タイミングが遅れると突発的な故障も発生していました。
CBM導入後は、振動パターンに“異常兆候”が現れた段階で交換するように変更。
結果、保全コストが30%削減され、突発停止もゼロに近づきました。
現場からは「壊れる前に対処できる安心感がある」と好評です。
鉄道業界でのCBM活用例:車両台車の亀裂監視
鉄道車両では「台車フレーム」に小さな亀裂が発生することがあります。
放置すれば大事故にもつながりかねませんが、全車両を毎日点検するのは現実的ではありません。
そこである鉄道会社では、車両に加速度センサーと画像診断装置を搭載し、台車の振動パターンや外観変化をAIで分析する仕組みを導入。
異常兆候が出た車両だけを重点的に点検する「選別保全」に切り替えました。
この結果、点検時間が30%短縮され、保全要員の業務負荷も軽減。重大事故のリスクを減らしつつ、効率的な運用を実現しています。
CBM導入の課題と対策
CBMには多くのメリットがありますが、導入にはいくつかの課題もあります。
1.初期コストがかかる
センサーやデータ通信環境の整備、状態監視システムの構築にはコストがかかります。部分的な導入から始め、効果を見ながら拡張するのが現実的です。
2.データの解釈にノウハウが必要
センサーから得られたデータは「数値」として存在しても、それが「どの程度の異常か」を判断するには専門的な知識や学習が必要です。AIや機械学習を活用する企業も増えています。
3.現場とのすり合わせ
「壊れてないのに交換?」という疑念や、「これまでの保全スタイルを変えることへの抵抗感」が現場にあることも。導入前の説明や、パイロット運用での効果検証が鍵となります。
従来の保全との違いは?
CBM(状態基準保全)が、従来の定期保全(TBM)と異なる点について整理します。
1.ムダな交換が減る=コスト削減
従来の定期保全では、「まだ使えるかもしれない部品」でも一定の期間ごとに交換していました。これは過剰保全とも呼ばれ、部品代・作業費ともにムダが生じやすい方法です。
CBMでは、実際の劣化状態に応じて必要なタイミングで保全を行うため、こうしたムダを削減できます。結果として、保全費用の最適化につながります。
2.故障の兆候をつかめる=突発停止の防止
定期保全でも、故障を完全に防げるとは限りません。
例えば「点検の翌日に壊れた」というケースも起こり得ます。
これに対してCBMは、振動・温度・音などの異常傾向をリアルタイムで検知できるため、故障の兆候にいち早く気づくことが可能です。
突発的な設備停止を未然に防ぐことができ、生産計画の乱れや納期遅れといったリスクも減少します。
3.状態が“見える”=品質と安全の安定化
CBMを導入すると、設備の状態が定量的なデータとして可視化されるようになります。これにより「勘や経験」に頼らない客観的な保全判断が可能になります。
状態のばらつきを抑えることで、製品品質の安定化にもつながります。
また、安全上重要な部位については、異常を早期に把握できることで事故の予防にもつながります。
まとめ <CBMの導入は“ムダとリスク”の両方を減らす投資>
CBMは、予知保全の一種として、今後さらに多くの業界で注目されると考えられます。
導入に際しては、全設備に一気に広げるのではなく、以下のステップが現実的です。
・故障リスクや保全コストの高い設備を特定
・センサーを設置して状態データを蓄積
・小規模なCBM運用で効果検証
・成功事例を社内に展開・共有
設備の状態を“見える化”することで、保全の精度や対応のタイミングを大きく改善することができます。
現場で「今の保全のやり方に限界を感じている」としたら、CBMという選択肢を検討してみる価値は十分にあるでしょう。


