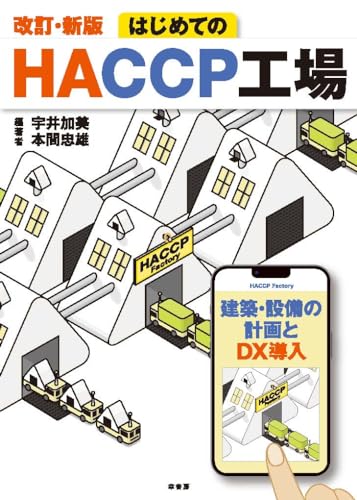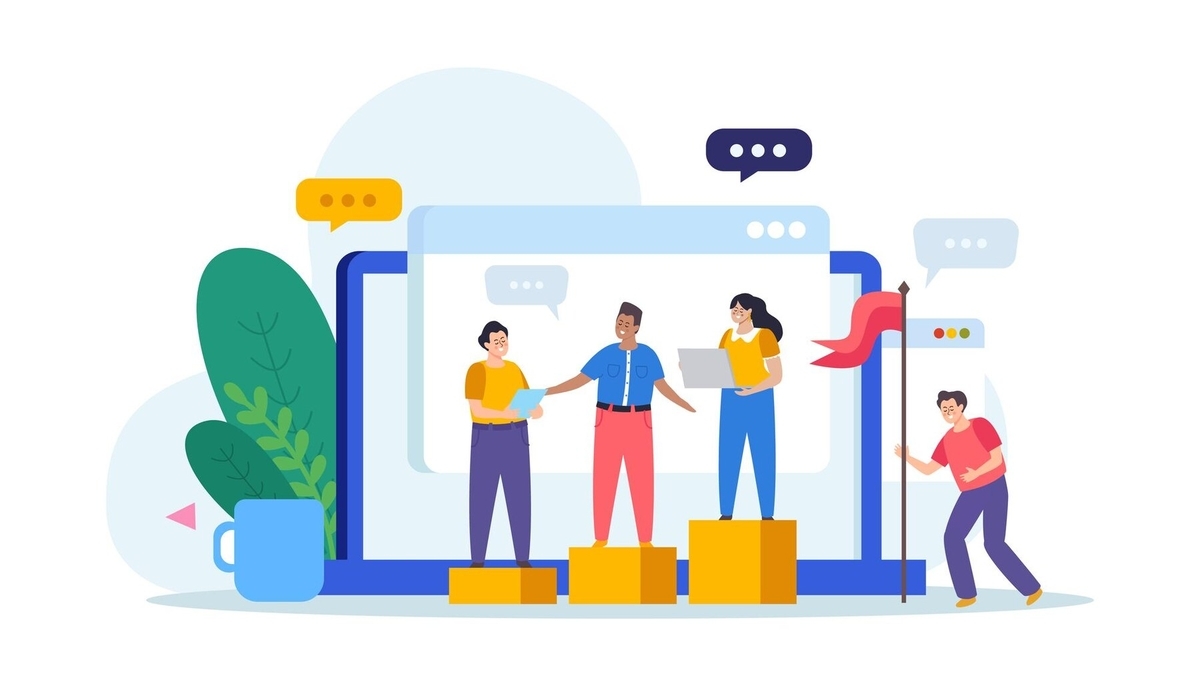
食品の安全性確保において、今や常識となりつつある「HACCP(ハサップ)」。
この中核を成すのが「CCP(Critical Control Point/重要管理点)」です。
2021年6月から、日本でもすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました(食品衛生法の改正)。
その中で、「どこをどう管理すればリスクを抑えられるのか」を明確にするのがCCPの役割です。
本記事では、CCPの基本的な考え方を解説した後、実際の製造現場での適用例を紹介。
食品業界を中心に、法規制や国際動向にも触れながら、ビジネスパーソンにもわかりやすく紹介します。
CCPとは何か? その基本的な考え方
CCPとは、「その工程での管理が失敗すると、製品が安全でなくなる可能性が高い」ため、特に重点的に管理すべきポイントのことです。
HACCPにおける7原則の中でも、以下のようなプロセスでCCPは定められます。
1.危害要因(ハザード)の分析
2.CCP(重要管理点)の決定
3.管理基準(CL:Critical Limit)の設定
4.モニタリング方法の設定
5.是正措置の決定
6.検証方法の設定
7.記録の保存
たとえば「加熱処理」は、病原菌を死滅させるための重要な工程であり、ここをきちんと管理しなければ食品の安全は確保できません。
よってこの「加熱工程」は典型的なCCPとなります。
CCP管理の具体例
実例①:冷凍ハンバーグ製造ラインでのCCP管理
冷凍食品工場では、例えばハンバーグの加熱処理工程がCCPとして設定されることが一般的です。
・CCPの工程:中心温度の加熱処理
・管理基準:中心温度が75℃以上で1分以上の保持
・モニタリング方法:温度センサーと記録装置の連携、作業者の定期チェック
・是正措置:規定温度未満の製品は廃棄または再加熱処理
このように、加熱不足による大腸菌やサルモネラ菌のリスクを防ぐため、温度と時間は厳密に管理されます。また、温度記録はデジタル保存され、トレーサビリティの証拠としても使われます。
実例②:乳製品(牛乳)の製造ラインにおけるCCP管理
乳製品の代表格である「牛乳」の製造では、「殺菌工程」が典型的なCCPです。
・CCPの工程:HTST(高温短時間殺菌:72℃で15秒)
・管理基準:温度・時間の両方を満たすこと
・モニタリング方法:連続監視システム+定期的な検証試験
・是正措置:殺菌不備ロットの廃棄、装置点検、再発防止対策の実施
国内外の乳業メーカーではこの殺菌工程の自動監視・アラート装置の導入が進んでおり、ヒューマンエラーの削減にも寄与しています。
実例③:給食センターにおけるCCP管理
学校給食や病院食などを扱う大量調理施設でも、CCPの設定は欠かせません。例えば、学校給食センターでは次のようなポイントがCCPに設定されます。
・CCPの工程:カレーの煮込み工程(肉や野菜の加熱)
・管理基準:中心温度85℃以上
・モニタリング:調理担当者が温度計で測定し、記録用紙に手書きで記録
・是正措置:再加熱処理+再測定
自治体によっては専用のHACCPチェックリストがあり、記録は保健所の立ち入り検査の際に提出義務があります。
関連法規と昨今の情勢:HACCP義務化が企業にもたらす変化
日本国内の法制度:食品衛生法改正によるHACCP義務化
2021年6月、改正食品衛生法が完全施行され、日本国内のすべての食品等事業者に対して「HACCPに沿った衛生管理の実施」が義務づけられました。この改正の背景には、国際的な食品衛生管理の潮流に遅れないよう、日本の食品安全管理水準を底上げする狙いがあります。
HACCP制度化により、事業者は次のいずれかの方式で衛生管理を行う必要があります。
・HACCPに基づく衛生管理(大規模・中堅企業向け):国際標準に沿った管理体制の整備が求められる
・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(小規模事業者向け):簡略化された形での記録・管理が可能
この制度は食品製造業だけでなく、飲食店、給食施設、食品卸売業など幅広い事業者が対象であり、従来の「事後チェック型」から「事前予防型」への転換を意味します。
国際動向:FSMA・Codexとの整合性が必須に
HACCPはもともとアメリカのNASAが宇宙食の安全を確保するために開発した手法で、現在ではCodex Alimentarius(FAO/WHO合同食品規格委員会)によって国際的なガイドラインが定められています。
このCodexに準拠することで、各国間で食品の安全性に関する共通理解が得られるようになります。
特に注目すべき国際法規として、米国のFSMA(Food Safety Modernization Act/食品安全強化法)があります。FSMAは2011年に制定された法律で、「食品の安全性は事前に管理すべきもの」というHACCPの考え方を強く反映しています。
米国に輸出する食品は、FSMAの「外国サプライヤー検証プログラム(FSVP)」などを通じて、HACCP対応を含む詳細なリスク評価と文書化が求められます。
同様に、EUでも食品安全規制(Regulation (EC) No 852/2004)においてHACCPの実施が義務付けられており、CCPの適切な設定・管理は輸出入の前提条件ともなっています。
中小企業への影響と支援制度
HACCP義務化は、特に中小企業や個人事業主にとって大きな制度変更です。従来のように経験と勘に頼った衛生管理から、科学的根拠に基づいた「記録と検証」の仕組みへの転換が求められるからです。
しかし、国や自治体も支援策を用意しています。たとえば以下のような取り組みが進んでいます。
・厚生労働省による手引書の公開:業種別にHACCP対応の方法が解説されている
・HACCP支援法(中小企業庁):施設改修やコンサル導入のための補助金制度
・地方自治体によるHACCP講習・認定制度:地域主導での普及支援
加えて、民間主導によるHACCP認証制度(例:JFS-B規格、FSSC22000、ISO22000など)も広がりを見せており、取引先からの要請によって導入を進める企業も増えています。
コロナ禍・食品偽装問題による社会的関心の高まり
2020年以降の新型コロナウイルス流行は、食品業界にも大きな衛生意識の変化をもたらしました。施設内の衛生管理だけでなく、作業者の体調管理や製品の外装清掃など、従来は意識されにくかった点も見直されるようになっています。
また、過去に起こった食品偽装や異物混入事件(例:冷凍食品への農薬混入事件、大手ホテルのメニュー偽装問題など)は、消費者の食品安全への不信感を高め、企業への説明責任がより重視されるようになりました。
CCPを含むHACCP対応は、こうした「信頼回復のためのエビデンス(証拠)」としても強力なツールとなっています。
まとめ
CCP(重要管理点)は、食品の安全性を確保するために不可欠な管理工程です。
HACCPの原則に基づき、リスクを最小限に抑えるために“どの工程を重点的に管理すべきか”を明確化します。
2021年の食品衛生法改正により、日本国内のすべての食品事業者に対してHACCPの導入が義務化され、これにより食品業界全体の衛生管理が強化されました。
CCPの管理は、単なる法的対応にとどまらず、消費者の信頼を獲得し、国際的な競争力を高めるための重要な手段です。
特に、加熱処理や殺菌などの具体例を通じて、現場での実践方法やリスク管理の重要性が浮き彫りとなります。
今後も食品業界における品質保証の標準として、CCPはますます重要な役割を果たしていくでしょう。