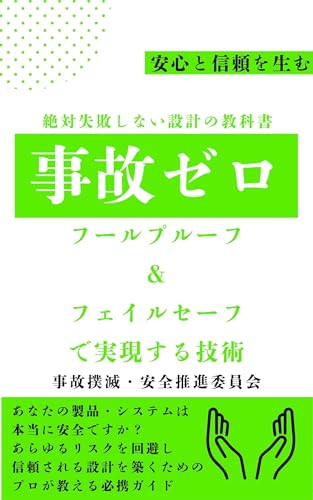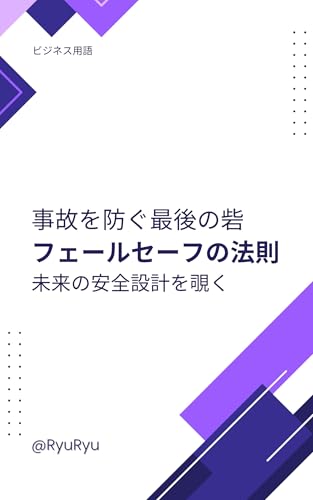製造業で欠かせない「冗長設計」とは何か?
この記事では、その意味や目的、冗長化の具体例をわかりやすく解説します。
生産設備・制御系・通信ネットワークなど、停止を防ぐ信頼性設計の実践ポイントを詳しく紹介します。
- 冗長設計とは何か?
- 冗長設計を採用する目的・効果
- 冗長設計の形式・方式(分類)
- 製造業における具体事例
- 冗長設計のデメリット・リスクとその対策
- IoT/スマートファクトリーにおける冗長化
- 冗長設計をうまく導入するためのポイント
- まとめ 信頼性設計としての冗長設計の意義
冗長設計とは何か?
冗長設計(じょうちょうせっけい、Redundant Design)とは、機械・設備・システムの一部が故障しても全体の機能を維持できるように、同じ機能を持つ要素を複数用意しておく設計手法です。
英語では「redundancy(冗長性)」と呼ばれ、信頼性設計(Reliability Design)の重要な考え方の一つです。
例えば、電源を2系統にしてどちらかが停止しても稼働を継続できるようにする、制御装置を二重化して異常時に自動切り替えする、通信経路を複数設けてネットワーク障害を防ぐ──これらはすべて冗長設計の具体例です。
このように冗長設計は、「止めない設計」「安全を守る設計」として、製造業やプラント、航空宇宙、医療、ITインフラなど、停止が許されない分野で広く採用されています。
近年ではスマートファクトリー化の進展により、設備や通信、データ管理までを含めたシステム全体の冗長化設計が求められるようになっています。
さらに、ISOやIECといった国際規格でも「冗長性の確保」は安全・品質の設計要件として明記されており、設計段階からの信頼性評価(RBD、FTA、FMEAなど)と一体化して検討することが重要です。
冗長設計を採用する目的・効果
冗長設計を導入する主な目的と効果には、以下があります。
・可用性向上,ダウンタイム抑制:どこかが故障しても稼働を維持できる
・信頼性強化:故障耐性を持たせ、安全余裕を確保
・安全性確保:安全系機構が故障しても代替系で制御を継続
・継続運用性:メンテナンス時も一方稼働を残せる構造
・顧客品質保証:システム停止による品質トラブル回避
特に、プラント、化学プロセス、医療機器、航空宇宙、自動車、安全制御システムなど、信頼性が非常に重要な分野で冗長設計は不可欠です。
プロセス産業では、制御系、補助電源、通信、ネットワークといった複数レイヤーで冗長化を設計する例が多く見られます。
冗長設計の形式・方式(分類)
冗長設計には複数の方式があります。主要な分類を以下に示します。
| 方式 | 説明 |
|---|---|
|
常時冗長(アクティブ冗長) |
並列構成で複数系統を常時稼働させ、故障時に即時切替。 |
| 待機冗長(スタンバイ冗長) | 平常時は予備系を休止させ、主系が故障時のみ起動。 |
| m-out-of-n 系方式 | n系統中、m系統が正常であれば機能継続とする方式。例:「2 out of 3」 |
| 多様化冗長(ダイバーシティ冗長) | 同じ機能を異なる原理または手段で実装し、相互補完的に保護する方式。 |
| 冗長系分離設計 | 同じ機能を持つ手段を二つ以上別場所に設置し、分離して冗長性を確保する方式。 |
製造業における具体事例
事例1:生産設備の二重化
例:包装機ラインの冗長化
ある食品工場では、包装工程の主要機械を2台並列構成(常時冗長)にしました。
主系でトラブルが起きても、もう1台が稼働を維持できるため、生産停止を最小限に抑えられます。
この方式では平常時に負荷分散することもでき、稼働効率の面でもメリットがあります。
例:樹脂成型機の予備装置
樹脂成型工場で、主要成型機の予備機を設置。
故障発生時には迅速に切り替えて生産を継続。大口受注や納期重視の製品には特に有効。
こうした二重化構成により、突発故障によるライン停止リスクを低減できます。
ただし、設備導入コスト・保守コストは高まるため、稼働率・リスク評価を慎重に行う必要があります。
事例2:制御系・安全系の冗長設計
例:安全システム(非常停止系)の冗長化
重機械設備やプラント設備では、非常停止ボタンや安全回路の故障が重大事故につながるため、冗長設計が必須です。
冗長系分離設計を取り入れ、安全機構を二重(または多重)に設けます。
たとえば、安全系回路を二重に設計し、片側回路が故障してももう片側で停止命令を維持する構成です。
さらに異なる回路原理(例:電気+油圧)を組み合わせる「多様化冗長」も使われます。
例:PLC制御装置の冗長化
工場の制御装置(PLC)は、主PLCと予備PLCを併設し、主系が異常を検知した場合に予備系に自動切り替えする方式があります。
これにより制御停止事故を回避できます。
例:ファン制御・ポンプ系
冷却ファン、ポンプなど補助機器についても、主要1台+予備1台の冗長構成(待機冗長)を使い、故障時に予備が即稼働する設計が多く見られます。
事例3:ネットワーク/通信系の冗長化
例:工場ネットワークの冗長構成
工場の通信ネットワークでは、スイッチ、ルータ、通信ケーブルなどが故障するとライン制御に重大影響を及ぼします。
よって、冗長経路の確保やリンク冗長化(リング構成、デュアルリンクなど)を設計します。
たとえば、スイッチ間をリング接続にし、一方が断線しても迂回通信で制御継続できる方式です。
例:制御ネットワークの冗長ルータ構成
制御ネットワークの基幹ルータを2台配置し、Active/Standby構成とすることで、1台故障時も通信途絶を防ぐ設計が一般的です。
例:PLC-センサー間通信冗長
センサーデータ収集やフィードバックループにおいて、通信パスを複数持たせておくことで、通信中断による制御異常を予防します。
IoT化・スマートファクトリー化の進展に伴い、こうした通信冗長性の設計が注目されています。
冗長設計のデメリット・リスクとその対策
冗長設計は万能ではありません。導入にあたっては以下の注意点があります。
・コスト増:設備・部材・保守費用が増える
・複雑性の増大:切り替えロジックや監視系が複雑に
・同時故障リスク:共通因故障(共通故障モード:CCF)に弱い
・運用負荷増大:定期点検・同期・試験が必要
・過剰冗長の無駄:冗長度の最適化が重要
これらを補うための対策としては、
・リスク評価、フェールモード解析(FMEA、FTAなど)を事前実施
・共通因故障を防ぐための絶縁多様性設計
・予防保全計画・定期試験の実施
・冗長化レベルの最適化(必要最小限)
・監視系・切替ロジックの信頼性確保
などを検討します。
IoT/スマートファクトリーにおける冗長化
近年、製造業ではスマートファクトリー、IoT/OT連携、デジタルツインなどの導入が進み、制御系・通信系・情報系が高度に統合されてきています。
この流れの中で、以下のような冗長化トレンドが顕著です。
・分散化制御+冗長通信:制御ノードを分散配置し、通信系を冗長化
・クラウド/エッジ併用設計:クラウドとエッジ装置双方に冗長構成を持たせる
・動的再構成冗長性:故障発生時に即時に最適な代替経路や構成を再構成
・セキュリティ+冗長化の統合設計:サイバー攻撃耐性を考慮した冗長性設計
・予測保全との融合:故障予兆検知と連動した冗長系切替制御
こうした進化により、単なるハード冗長から、ソフト/制御レベルでの冗長設計が重視されるようになっています。
冗長設計をうまく導入するためのポイント
・リスクと損失評価を最初に行う:停止リスクや故障頻度、停止コストを定量化
・冗長度の最適化:必要以上に重複させず、効果対コストのバランスを取る
・多様化設計の併用:完全な二重化のみでなく、異なる技術や構造を併用
・切替ロジック,監視系の信頼性設計:偽切替や誤動作防止設計を慎重に
・定期試験,監視,保守計画の整備:バックアップ機構の健全性を維持
・段階導入,試験運用:冗長系を段階的に導入し、障害時の挙動を確認
・関係部門との協調:電気、制御、IT、保全部門間で設計調整
・将来拡張性を考慮する:将来的な設備追加や制御進化を見据えた冗長設計
これらを押さえておけば、冗長設計の導入性・維持性を高められます。
まとめ 信頼性設計としての冗長設計の意義
冗長設計は、単なる冗長化(無駄な重複)ではなく、信頼性確保と事業継続性を支える設計の柱です。
製造現場では、設備停止や制御喪失が生産・品質に直結するため、適切な冗長設計は不可欠です。
ただし、その実現にはコスト・複雑性・運用性のバランスを取ることが重要です。
法規・安全設計上の要件、将来のスマート化・IoT化の見通しも踏まえながら、最適な冗長構成を検討・実装していくことが、これからの信頼性設計には求められます。