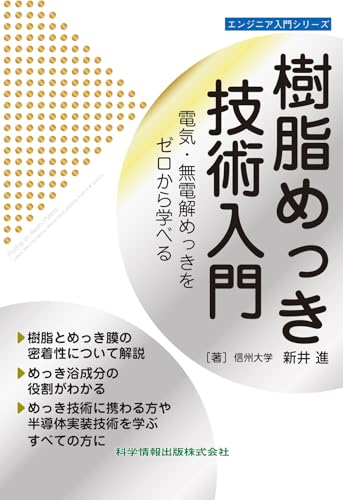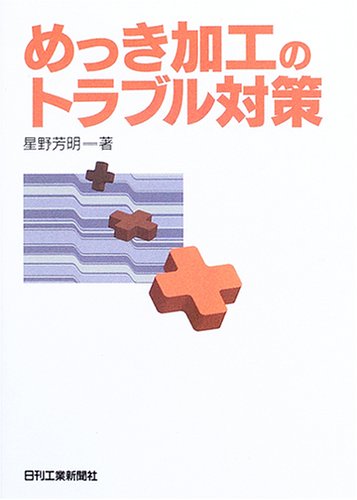めっき剥がれ(Peeling of plating)は、見た目の問題だけでなく、腐食や導通不良、機能低下といった重大なトラブルを引き起こす要因です。
特に製造業では、外観検査での発見が遅れれば、製品保証やクレーム対応に直結します。
本記事では、めっき剥がれの代表的な原因と防止策を、実際の製品例を交えて解説します。
めっき剥がれとは?
めっき剥がれとは、基材(金属や樹脂)とめっき皮膜との界面密着が失われる現象です。
外力、熱応力、電位差、化学反応などの影響により、界面が分離し、めっき層が浮き上がったり、剥離したりします。
代表的な発生箇所
・自動車部品:亜鉛めっきボルト、ニッケルめっきバンパー部材
・電子機器:プリント基板の銅めっき、コネクタ端子の金めっき
・家電製品:装飾めっきパネル、電極部の防錆めっき
めっき剥がれが一度発生すると、下地金属の腐食進行が加速し、最終的に構造強度や電気特性を損ないます。
めっき剥がれの主な原因
原因①:密着不良(界面の物理的問題)
最も多い原因は、下地とめっき層の密着不良です。
これは、表面の油脂・酸化膜・異物残りなどが原因で、めっき皮膜が基材にしっかり結合できないことによって起こります。
原因の詳細
・脱脂,酸洗工程が不十分(油膜や酸化皮膜の残存)
・サンドブラスト,エッチング不足(表面粗さ不足)
・樹脂めっきの場合、プラズマ処理や化学エッチング不良
事例:自動車用ボルトの亜鉛めっき
自動車の足回りに使用される亜鉛めっきボルトで、熱処理後の酸化スケール除去不足によりめっき密着不良が発生。
走行中の振動で剥がれが進行し、錆の拡大につながった例があります。
防止策
・前処理(脱脂・酸洗・活性化)の標準化と記録管理
・表面粗さ(Ra)の定量管理
・中間洗浄水の純度(導電率)の定期確認
プラズマ処理・サンドブラスト条件の最適化
密着不良は「工程内で見えにくい欠陥」なだけに、前処理品質のモニタリングがカギになります。
原因②:電位差(ガルバニック腐食による剥離)
異なる金属を組み合わせた場合に発生するガルバニック腐食(電位差腐食)も、めっき剥がれの原因として見逃せません。
めっき層と下地金属の電位差が大きいと、腐食電流が流れ、界面が劣化して剥離します。
電位差腐食のメカニズム
たとえば、銅の上にニッケルめっきを行う場合、両者の電位差は比較的小さいため安定ですが、アルミ上にニッケルめっきを行うと、電位差が大きく、湿気環境下でアルミが腐食して界面が剥がれやすくなります。
事例:電子機器のコネクタ端子
コネクタの下地に銅合金を使用し、その上にニッケル・金めっきを施す構造では、ピンホール部からの腐食進行により界面が劣化。
最終的に金めっき層が剥離し、接触抵抗が増大する不具合が発生しました。
防止策
異種金属間の電位差(電極電位)を考慮した材質選定
・中間バリア層(例:ニッケル中間層)の採用
・ピンホール検査(ポロシティテスト)の実施
・防湿コーティングによる電解液環境の遮断
電位差を軽視すると、表面処理後の長期信頼性が大きく損なわれるため、設計段階での材料選定が重要です。
原因③:下地処理の不備(化学的な落とし穴)
下地処理とは、基材表面を化学的に処理し、めっきが密着しやすい状態に整える工程です。
この工程での薬液管理・濃度管理が不適切だと、皮膜形成が不安定になり、部分的な剥離が起こります。
よくある不具合
・酸洗い後の中和不十分 → 残留酸が後工程で反応
・活性化液(塩化パラジウムなど)の濃度低下 → 樹脂めっきの密着不足
・リンス工程の水質劣化 → 塩素イオン残留による界面腐食
実例:樹脂製コネクタへの無電解ニッケルめっき
樹脂部品に無電解ニッケルめっきを施す際、触媒付与液の劣化に気付かず使用を続けた結果、局部的な密着不良が発生。
製品出荷後、数カ月で剥がれが多数報告され、工程見直しと液管理基準の改定が行われました。
防止策
・前処理液,活性化液の濃度,pH,温度の定期記録
・処理液の寿命管理と交換履歴のトレーサビリティ化
・薬液ごとの管理チャート(SPC)導入
・樹脂めっきでは、試験片による密着性確認試験を日常化
下地処理は化学の世界であり、見えない変化をデータで監視する体制が欠かせません。
製造現場での見落としポイント
めっき剥がれの多くは、単一要因ではなく複合的な要因によって発生します。
以下のような盲点に注意が必要です。
見落としやすい要素
・めっき厚さのバラツキ(過薄部で応力集中)
・加工応力(曲げ,圧入)による界面損傷
・熱膨張差(異材接合部の熱応力)
・保管環境(高湿度,汗,薬品ミスト)
・表面保護膜の劣化(クロメート,封孔処理の効果低下)
検査・評価方法
めっき密着性を確認するための代表的な試験方法を以下に示します。
| 試験法 | 内容 | 判定基準 |
|---|---|---|
| テープ試験 | テープを貼って剥がれを観察 | 剥離・転写がないこと |
| クロスカット試験 | 格子状に切り込み、剥離状態を確認 | 0〜5級(0級が良好) |
| 曲げ試験 | 板材を一定角度に曲げ、剥がれを観察 | 剥離・割れがないこと |
| 塩水噴霧試験(SST) | 腐食環境下での密着性を評価 | 所定時間後も剥離なし |
めっき密着性評価は、製品の長期信頼性を確保する重要工程です。
テープ試験やクロスカット試験で初期剥離を確認し、曲げ試験で使用応力下の挙動を評価します。
さらに塩水噴霧試験で湿潤環境下の耐久性を確認することで、量産前と定期検証の両面からめっきの健全性を把握できます。
めっき剥がれ防止方法
製造現場で再発防止を実現するためには、設計・材料・工程の三位一体管理が必要です。
設計段階
・電位差を考慮した材質選定
・めっき厚さ,均一性の設計値を明示
・加工応力を最小化する構造設計
材料選定段階
・表面粗さ,清浄度の管理値設定
・めっき液との相性確認試験
工程管理段階
・前処理液,活性化液の定期交換
・めっき条件(電流密度,温度)の自動記録
・サンプル片による剥離検査の標準化
まとめ:見えない界面の品質を「管理」で守る
めっき剥がれは、目視検査では初期段階を見逃しやすく、工程データと設計配慮の両輪管理が不可欠です。
特に、自動車・電子機器・精密装置などでは、微小な剥がれが長期信頼性低下や保証コスト増大に直結します。
「密着不良」「電位差」「下地処理不備」という3大要因を理解し、設計・前処理・工程監視の全段階で一貫した品質保証体制を築くことが、剥がれゼロを実現するために必要です。
![図解入門 よくわかる 最新 めっきの基本と仕組み[第3版] 図解入門 よくわかる 最新 めっきの基本と仕組み[第3版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uIXN2Ie2L._SL500_.jpg)