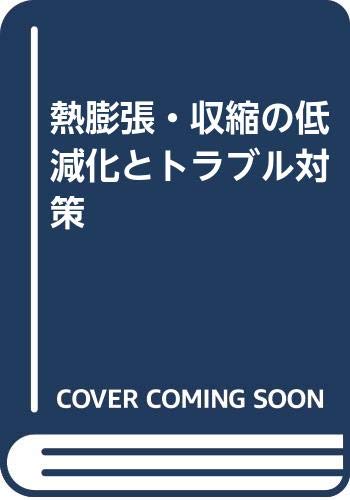温度変化によって金属や樹脂などの材料が膨張・収縮する現象「熱膨張」は、製造業のあらゆる分野で避けて通れないテーマです。
とくに異素材を組み合わせた構造や、高温・低温を繰り返す環境では、熱応力による歪みや割れが発生しやすく、製品の寿命や信頼性を大きく左右します。
本記事では、熱膨張と熱応力の基礎から、代表的なトラブル事例、設計段階での対策方法まで、製造業の現場で役立つ形で解説します。
熱膨張とは
熱膨張とは、物質が温度上昇によって体積または長さを増す現象のことです。
分子の運動エネルギーが増加し、原子間距離が広がるために起こります。多くの材料では温度上昇で膨張し、温度低下で収縮します。
熱膨張率とは
材料ごとに「どの程度膨張するか」を示す指標が線膨張係数(熱膨張率)です。
単位温度あたりの伸び率を表し、一般的に 10⁻⁶/K(1℃あたりの変化率)で表記されます。
| 材料 | 線膨張係数(×10⁻⁶/K) |
|---|---|
| アルミニウム | 約23 |
| 鉄鋼 | 約12 |
| 銅 | 約17 |
| シリコン | 約3 |
| エポキシ樹脂 | 約60〜80 |
このように、金属・樹脂・セラミックスなどの膨張率は大きく異なります。
この差が、異素材接合部での応力集中や剥離の原因になります。
熱応力とは
材料は温度が変化すると膨張したり収縮したりしますが、自由に動ける場合は特に問題はありません。
しかし、部品や構造物が固定されていて自由に伸び縮みできない場合、内部に力が発生します。これを熱応力(Thermal Stress)と呼びます。
例えば、金属の棒を両端でしっかり固定したまま加熱すると、棒は長くなろうとしますが、固定によって伸びられません。
この「伸びたくても伸びられない状態」が応力として材料内に現れます。
逆に冷却される場合には、縮もうとする力が阻まれて引張応力が発生します。
熱応力の発生メカニズム
たとえば、鉄板が高温で加熱されて膨張しようとしても、周囲の構造体に固定されている場合は動けません。
この「動けない状態での膨張しようとする力」が応力となり、温度差が大きいほどその力は増大します。
この熱応力は、材料の強度限界を超えると以下のような歪み・割れ・剥離として顕在化します。
・歪み:部材が曲がったりたわんだりする
・割れ:応力が大きくなると破断が発生
・剥離:異素材接合部で材料がはがれる
熱応力の基本式と計算方法
材料が膨張・収縮を拘束されたときに発生する熱応力(σ)は、次の式で求められます。
各記号の意味
:発生する熱応力(Pa)
:ヤング率(材料の弾性率、Pa)
:線膨張係数(1/K)
:温度変化(K または ℃)
この式は、材料が完全に拘束されて自由に膨張できない場合の理論値です。
実際の構造では、一部が動けるためこの値より小さくなります。
計算例
条件
・材料:炭素鋼(E = 210 GPa, α = 12×10⁻⁶ /K)
・温度上昇:ΔT = 100℃
・完全拘束されていると仮定
計算
結果
約252 MPaの熱応力が発生。これは一般的な構造用鋼の降伏強さ(約250〜350 MPa)に近く、温度変化だけで塑性変形や割れが起こり得るレベルです。
このように、わずか100℃の温度差でも拘束条件によっては大きな応力が発生します。
設計段階で温度変化を想定し、膨張逃げやスライド構造を設けることが重要です。
熱膨張・熱応力による代表的なトラブル事例
事例1. 金型の割れ・摩耗(自動車部品製造)
自動車用樹脂部品の射出成形では、金型が加熱・冷却を繰り返します。
型材の一部が局所的に高温になると、熱膨張差により微小なクラック(割れ)が発生します。
これが繰り返されることで疲労割れが進行し、最終的には金型破損につながります。
対策例
・均一加熱,冷却が可能な冷却回路設計
・熱伝導率の高い型材(例えばベリリウム銅)を適所に使用
・FEM解析による温度分布予測
事例2. 電子基板のはんだクラック(電子機器業界)
プリント基板(FR-4)と半導体チップ(シリコン)では熱膨張率が大きく異なります。
高温動作やリフローはんだ工程で、この膨張差がはんだ接合部に応力を集中させ、クラックやボイド発生を引き起こします。
対策例
・中間層に低弾性材料(アンダーフィル)を充填
・熱サイクル試験での耐久性評価
・チップサイズの最適化とフレキシブル基板採用
事例3. ボルト緩み・機械構造の歪み(産業機械)
鋼製フレームにアルミ部材を取り付けた場合、運転中の温度上昇でアルミが大きく膨張します。
ボルト締結部では熱応力による座面圧の変化が起こり、緩みやガタつきにつながることがあります。
対策例
・スプリングワッシャやディスクスプリングの使用
・材料の熱膨張差を考慮したスライド構造の採用
・定常運転温度に合わせた締付トルク設定
事例4. 熱歪みによる寸法狂い(工作機械・精密装置)
精密加工機では、温度上昇によってベッドや主軸がわずかに伸びるだけでも、加工精度に大きく影響します。
たとえば、5℃の温度変化で鋼構造(長さ1m)は約60μm伸びます。
対策例
・温度安定室での加工(恒温環境)
・低膨張材(インバー合金など)の採用
・温度補正機能付きNC制御
設計段階での考慮ポイント
①材料選定
異素材間の接合では、線膨張係数の差を最小化する組み合わせが基本です。
たとえば、アルミと鋼を接合する場合、中間材として銅を挟むことで熱膨張差を緩和できます。
また、電子部品では、シリコンと膨張率が近いセラミックス(AlNなど)を基板に用いる設計も一般的です。
②構造設計
固定端を減らして「膨張逃げ」を確保することで、熱応力を大幅に低減できます。
具体例として、配管システムでは「エキスパンションジョイント」や「ループ配管」を設け、温度上昇時の伸びを吸収します。
機械構造では、片側固定・片側スライド構造が有効です。
③熱伝導の均一化
局所的な温度上昇があると、同一素材でも部分的に異なる膨張が起こり、応力が集中します。
・均一な加熱,冷却流路の設計
・熱伝導グリスや放熱フィンの使用
・熱シミュレーションによる温度分布の事前確認
これらの工夫で温度ムラを最小化できます。
④製造、組立段階での温度考慮
部品組立時の温度と実使用温度が大きく異なる場合、初期歪みが発生します。
たとえば、高温環境で使用するアルミ製治具を室温でボルト固定すると、稼働時に膨張し締付けが過大になることがあります。
組立時温度を基準化したり、温度補正を考慮した公差設計が重要です。
熱応力解析と評価方法
①FEM解析による熱応力シミュレーション
現在では多くの設計現場でFEM(有限要素法)解析が活用されています。
温度分布を与え、各部の変形・応力を数値的に予測できます。
特に金型、電子基板、構造物などでは、熱サイクルを想定した時間依存解析が有効です。
②実験的評価(熱サイクル試験・ひずみゲージ計測)
実機評価では、以下のような試験が一般的です。
・熱サイクル試験(−40〜+125℃などの繰返し)
・赤外線サーモグラフィによる温度ムラ観察
・ひずみゲージを用いた熱応力測定
解析と実験の両面から評価することで、設計の妥当性を高められます。
各業界での具体的な応用例
自動車業界:エンジン・EVバッテリーの温度設計
エンジンブロックや排気系では、運転時に数百度の温度差が発生します。
異材接合部では熱膨張差によるガス漏れやクラックが懸念されるため、膨張を吸収するガスケット材(グラファイトやメタルコンポジット)が採用されています。
EV分野では、バッテリー冷却プレートに用いるアルミと樹脂の接合部に熱応力が集中しやすく、接合部のフローティング構造で逃げを確保する設計が主流です。
半導体・電子業界:高密度実装での熱歪み対策
CPUやパワーモジュールでは、発熱密度が高く、材料の膨張差が寿命を左右します。
シリコンチップと銅基板の間に低膨張のセラミック層(Si₃N₄など)を挟む構造が広く用いられています。
さらに、車載電子部品ではAEC-Q100に準じた熱サイクル耐久試験で検証が行われます。
プラント・配管設備:熱膨張吸収構造の重要性
ボイラー配管や化学プラントでは、運転温度が300℃を超えることもあります。
配管の熱伸びを吸収しない設計では、溶接部に大きな応力が集中し、疲労亀裂や漏洩事故を引き起こすリスクがあります。
対策として、蛇腹形エキスパンションジョイントや可動支持構造を設けるのが一般的です。
まとめ
熱膨張や熱応力は、完全にゼロにすることはできません。
重要なのは、それを想定内に収める設計と管理です。
・材料特性(膨張率,弾性率)の理解
・温度分布,拘束条件の把握
・熱応力の解析と実機評価
これらを組み合わせることで、温度変化に強い信頼性設計が実現します。
熱膨張を敵として扱うのではなく、「熱を前提とした設計」に切り替えることが、長寿命・高信頼な製品づくりに有効です。