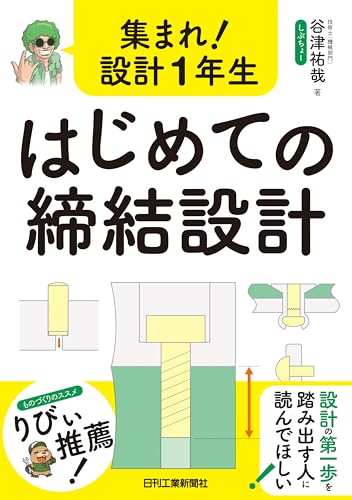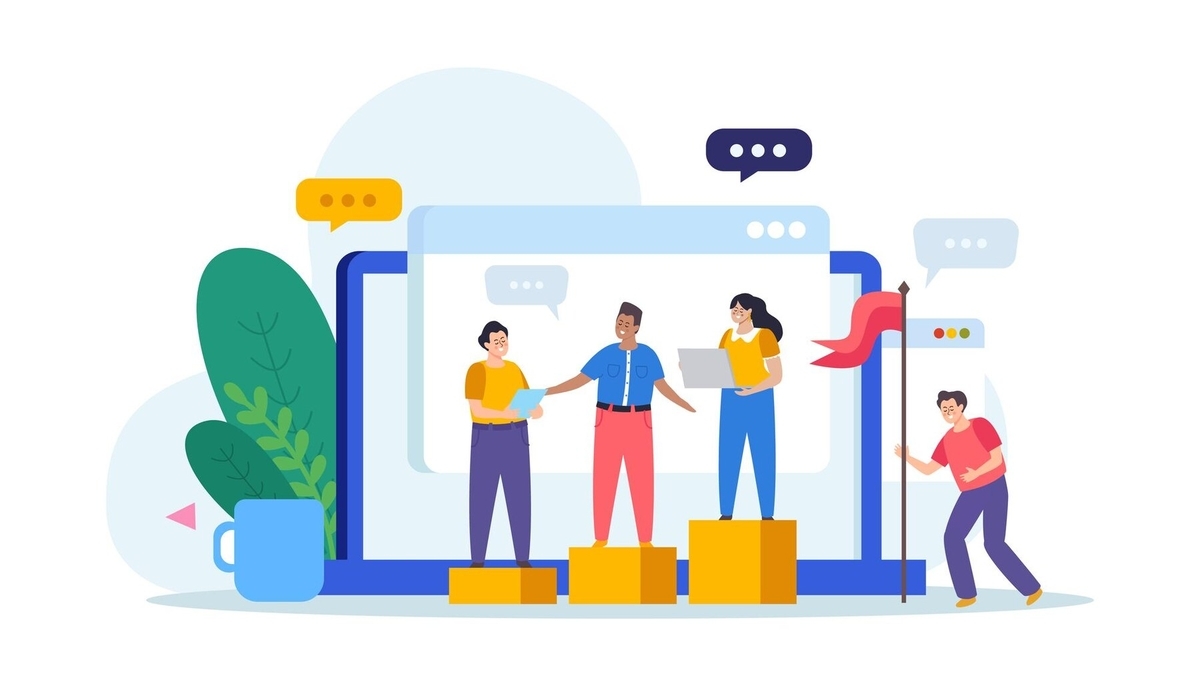
「うちの現場は多品種少量生産だから、MSAなんて無理だよ」
そう感じている現場リーダーや品質担当の方も多いのではないでしょうか。
確かに、多品種少量生産では同一製品がまとまった数で流れることは少なく、MSAの前提条件(繰返し測定、一定条件下の再現性確認)が難しくなります。
しかし、「やらない」ではなく「どうやってやるか」という視点で工夫すれば、多品種少量の現場でも測定システムの信頼性を担保することは十分可能です。
この記事では、MSAの基本から、多品種少量での実施上のポイントと注意点について詳しく解説します。
- そもそもMSA(測定システム解析)とは?
- 多品種少量生産におけるMSAの難しさ
- 多品種少量でMSAを行うための実施ポイント
- 実施時の注意点とよくある落とし穴
- MSAの評価基準
- 多品種少量生産におけるMSAの考え方
- まとめ
そもそもMSA(測定システム解析)とは?
MSA(Measurement System Analysis)とは、測定システムがどれだけ正確で信頼できるかを評価するための手法です。
製造業では、製品の合否や工程改善など多くの判断が測定結果に基づいて行われるため、測定そのものの信頼性を保証することは非常に重要です。
MSAでは、次のような観点から測定誤差の原因を特定します。
・繰返し性(Repeatability):同一測定者・同一機器で同じものを測定したときのばらつき
・再現性(Reproducibility):異なる測定者・機器で測定したときのばらつき
・偏差(バイアス):真の値とのズレ
・直線性:測定範囲内でバイアスが変化する傾向
・安定性:時間とともに測定値が変化する傾向
これらを定量的に分析することで、「その測定値は工程管理や合否判定に使える水準か?」を評価します。
信頼できない測定では、合格品を不合格と判定したり、不良品を見逃すリスクが高まるため、MSAは品質管理の基盤とも言える存在です。
多品種少量生産におけるMSAの難しさ
MSAの一般的な実施方法では、同じ部品を複数回測定する必要がありますが、多品種少量生産ではこの条件を満たすのが非常に難しくなります。
この種の生産形態で直面しやすい課題には、以下のようなものがあります。
・同一製品がまとまって生産されないため、繰り返し測定のためのサンプルが確保できない
・製品ごとに寸法・形状・材質・測定箇所が異なるため、測定手順の標準化が困難
・検査後すぐに次工程へ流れるため、再測定や複数人での測定が物理的に難しい
・測定方法が品番ごとに異なり、毎回異なる治具や手順が必要になる
こうした背景から、多品種少量の現場では「MSAは理屈では分かるけど、現場では回らない」という声が多く聞かれます。
しかし、課題を抱えているからこそ、現実に即した柔軟なMSAのやり方を模索する意義があるとも言えます。
多品種少量でMSAを行うための実施ポイント
ポイント①:代表品番を用いた代表測定
すべての品番に対してMSAを実施するのではなく、代表的なサイズ・形状・測定方法を持つ品番を選定して、MSAを代用的に実施します。
例:
・φ10~φ50まである製品群 → φ30を代表としてゲージR&Rを実施
・長さ測定が共通している複数品番 → 1品番でMSAを代表評価
こうすることで、実施負荷を下げつつ、測定システムの傾向を把握することができます。
ポイント②:測定方法ごとのMSAに切り替える
MSAは「製品に対して」ではなく、「測定手段に対して」実施するという視点に切り替えるのも有効です。
例:
・ノギスによる外径測定 → ノギスそのものの繰り返し性・再現性を評価
・圧力試験機によるリーク測定 → 測定機+治具のセットで安定性を評価
このように、「測定器+作業者+方法」単位でMSAを管理することで、品番の多様性に引きずられずに測定システムの妥当性を確認できます。
ポイント③:再測定のタイミングを仕組みに組み込む
「再測定ができない」は多品種少量の悩みの一つですが、製品の移動タイミングに注目すると改善の余地があります。
例:
・製品をすぐに次工程へ流さず、「保留置き場」に一定時間留める
・測定後すぐに他者が同一製品を再測定できるよう、簡易ループを設ける
・治具や測定器の温度変化を考慮し、測定間隔を一定に管理
こうした「測定→再測定」を回す仕組みづくりが、実施の現実性を高めます。
実施時の注意点とよくある落とし穴
・「品番ごとのMSAが必要」と思い込まない
品番ごとに実施しようとすると、MSAが形骸化する恐れがあります。前述のように、「測定方法単位での代表評価」に切り替えましょう。
・測定者を“実作業者”から選定する
MSAは測定のバラつきを評価するため、実際に測定作業を行う作業者が参加者であることが前提です。品質保証部門だけが参加しても、実態は見えません。
・評価条件を必ず記録・共有する
「誰が、何を、どう測定したか」の条件を明確にし、再現可能な形で記録しましょう。多品種少量では特に測定条件がばらつきやすいため、前提条件の共有と標準化が重要です。
MSAの評価基準
代表的なGRRの評価基準は次の通りです。
・GRRが総変動の10%以下:理想的(十分に良好)
・10~30%:条件付きで使用可能(改善の余地あり)
・30%以上:測定システムとして不適(対策が必要)
ただし、多品種少量生産では測定対象の変動が大きいため、厳密な数値よりも傾向分析や相対比較に重きを置くのが現実的です。
多品種少量生産におけるMSAの考え方
多品種少量生産の現場では、理想的なMSAを一度に完遂しようとすると、サンプル確保や作業負荷、リードタイムへの影響が大きくなり、かえって現場の負担が増します。
そのため、「完璧な測定評価」よりも「継続的な改善」を意識することが重要です。
たとえば、製品ごとに完全なGRR評価が難しい場合でも、共通する測定機器(ノギス、マイクロメータなど)についてだけ定期的にGRR評価を実施し、測定者のばらつきを管理するという手法があります。
あるいは、工程監査のタイミングで、ランダムに抜き取った製品を複数人で再測定し、測定者間の差を観察する「簡易MSA」を定期的に実施する方法も有効です。
重要なことは、できる範囲でデータを蓄積しばらつきを減らす意識を育てること。
一度の分析で全てを明らかにしようとせず、少しずつ測定信頼性を高めていく方が、実務的で持続可能な品質改善につながります。
まとめ
MSAは、本来「正しい品質判断を行うために欠かせない手段」ですが、多品種少量生産の現場では、その導入方法に柔軟性が求められます。
「同じ条件で10回測れないから実施できない」と諦めるのではなく、製品群をカテゴリで分けて代表モデルで評価したり、測定者ごとの傾向を比較する簡易手法を取り入れるなど、運用に工夫を凝らすことがカギです。
たとえば、試作フェーズで得られた測定データを使ってGRRの簡易評価を行う、あるいは工程内のQC工程表に「測定バラつき注意箇所」を明示しておくといった運用面の工夫も有効です。
完璧なルールやフォーマットにとらわれず、現場が実行可能な方法で「測定の信頼性」を担保し続ける仕組みを作ることが、品質を守るうえでの真の強みになります。