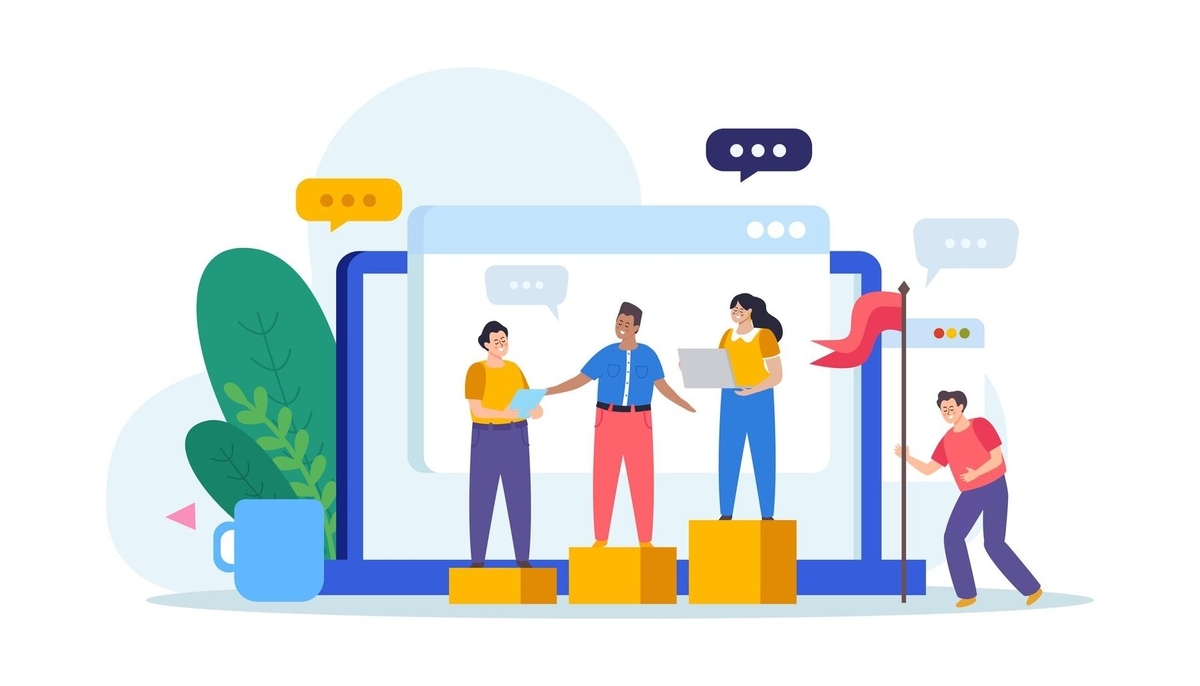
製造現場で「スペック外なのに、なぜかOK判定になっている」といった混乱が起きることはないでしょうか?
その背景には、「許容範囲(スペック)」と「管理範囲(管理限界)」という、2つの異なる概念の混同があります。
品質管理の基本として知っておきたいこの違いと、現場での正しい使い分けについて詳しく解説します。
- 許容範囲(Specification Limit)とは?
- 管理範囲(Control Limit)とは?
- 許容範囲と管理範囲の比較
- 実務での混乱例とその対策
- 関連用語の理解も重要:Cpkとの関係性
- なぜこの区別が重要なのか?
- まとめ
許容範囲(Specification Limit)とは?
「許容範囲」とは、顧客が求める品質条件を満たすための寸法や性能の許容される上下限を指します。いわゆるスペックとも呼ばれ、製品図面や製品仕様書に明記されることが一般的です。
たとえば、ある部品の外径が「φ10.00±0.05」となっていれば、許容範囲は「φ9.95~10.05」となります。この範囲内であれば、その製品は顧客要求を満たしていると見なされ、合格(OK)品となります。
つまり、許容範囲を外れた製品はNG(不良品)であり、そのまま出荷すればクレームや品質事故の原因になりかねません。
管理範囲(Control Limit)とは?
一方、「管理範囲」とは、工程が安定しているかどうかを監視・判断するための基準です。こちらは製品の規格とは異なり、主に統計的品質管理(SQC)で使われます。
管理範囲は、工程能力指数(Cp, Cpk)や過去の測定データを基に、平均±3σ(標準偏差)などの統計手法で設定されます。一般的に「管理上限(UCL)」「管理下限(LCL)」と呼ばれ、管理図などに使用されます。
つまり、管理範囲を逸脱することは、「不良品が出た」ことを意味するのではなく、工程に異常や変動が生じた可能性があるという警告を意味します。
許容範囲と管理範囲の比較
| 項目 | 許容範囲(スペック) | 管理範囲(管理限界) |
|---|---|---|
| 目的 | 顧客要求を満たすため | 工程の安定性を監視する |
| 設定主体 | 顧客、設計部門 | 品質管理部門、生産現場 |
| 基準 | 図面、公差 | 統計計算(±3σなど) |
| 違反時の判断 | 不良品(NG) | 異常信号(要原因追及) |
| 表示場所 | 図面、検査基準書 | 管理図、QC七つ道具 |
このように、許容範囲=製品のOK/NG基準、管理範囲=工程の異常検知ツールという役割の違いがあります。
これを混同すると、不良の見逃しや過剰な手直し対応につながりかねません。
実務での混乱例とその対策
・ケース1:スペック外だが管理範囲内 → 出荷してしまった
ある加工部品で、測定結果が10.06mm(許容範囲:9.95~10.05、管理範囲:9.90~10.10)だった場合、「管理範囲内だからOK」と誤認し、不良品が出荷されたというケース。
対策:検査判定には必ず「許容範囲」を使用する。管理範囲は工程改善の指標であり、判定基準ではないと現場で徹底する。
・ケース2:スペック内だが管理範囲外 → 合格なのに手直しや再検査が発生
同じく寸法10.00±0.05の部品で、測定値が10.00であっても、直近の傾向から統計上の管理限界(例えば9.95〜10.05)を外れていた場合、異常処理がなされていた例もあります。
対策:スペック内であれば合格だが、「管理限界逸脱=工程異常の可能性」として分けて考える。製品自体を再検査するのではなく、原因調査を優先する。
関連用語の理解も重要:Cpkとの関係性
工程能力指数(Cpk)は、工程がどれだけ許容範囲内に収まる安定性を示す指標で、管理範囲と許容範囲の関係性を数値化したものです。
・Cpkが高い(例:1.67以上)=工程が中心に寄っており、ばらつきも小さい
・Cpkが低い(例:1.00未満)=工程のばらつきが大きく、スペック外のリスクが高い
つまり、Cpkを用いて「管理範囲が許容範囲に対してどれくらい余裕があるか」を確認することは、品質リスクの事前評価につながります。
なぜこの区別が重要なのか?
「許容範囲」と「管理範囲」を混同してしまうと、次のような問題が発生します。
・本来OKな製品を不良と判断して無駄なロスが出る(過剰品質)
・本来NGな製品を管理範囲内だからと誤って出荷してしまう(品質事故)
・品質不具合の真の原因が見えず、再発が止まらない
これらを防ぐには、製品品質の判定基準と、工程品質の監視基準を切り分けて運用する必要があります。
現場に明確な基準を設け、教育・訓練を徹底することが、品質トラブルの未然防止につながります。
まとめ
「管理範囲=異常の予兆」、「許容範囲=顧客の要求品質」。
品質管理において、「管理範囲」はあくまで工程の安定性を維持するための内部基準であり、「許容範囲」は製品の合否を決める顧客目線の基準です。
スペックと統計管理を混同せず、それぞれの役割を正しく理解することで、不要な混乱を防ぎ、信頼性の高い品質管理体制を構築できます。


