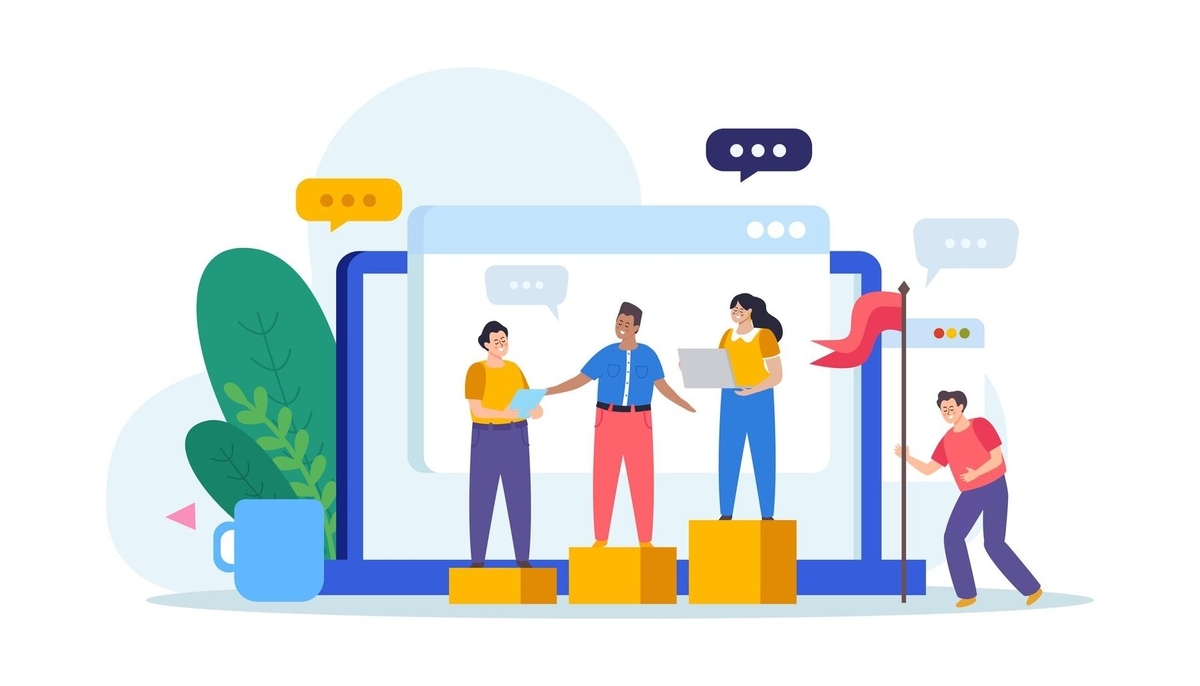
製造業や品質管理の現場で頻繁に使われる「PPM」という指標。特に量産製品においては、顧客との品質保証契約や内部KPIとして使われるケースも多く、「10PPMを切ること」などが目標として掲げられることがあります。
本記事では、PPMの定義や計算方法から、目標の立て方、実際の品質改善への活用法までを分かりやすく解説します。
- PPMとは何か?基本の定義と計算式
- PPMの目標値設定はどうする?業界ごとの目安と考え方
- 社内での目標設定のポイント
- PPMを用いた品質改善アプローチ
- PPMと工程能力指数(Cpk, Ppk)の関係性
- まとめ:PPMは「現場の品質スコア」である
PPMとは何か?基本の定義と計算式
PPMとは「Parts Per Million」の略で、100万個あたりにどれだけ不良があるかを示す品質指標です。不良率をより細かい単位で可視化するために用いられます。
例えば、不良率が0.1%であれば、PPMでは1,000PPMとなります。
計算式
PPMは次の式で求められます
PPM = (不良数 ÷ 生産数)× 1,000,000
例:
生産数:50,000個
不良数:25個
→ PPM = (25 ÷ 50,000) × 1,000,000 = 500PPM
このように、PPMは歩留まりや不良率をより直感的に表現するための指標といえます。
PPMの目標値設定はどうする?業界ごとの目安と考え方
PPMの目標は業界や顧客要求によって異なります。一般的に、品質要求が厳しい業界ほどPPMの許容範囲は狭くなります。
・自動車業界
自動車部品業界では、サプライヤーに対して「10PPM以下」といった厳しい目標が求められることがあります。これは「100万個に10個の不良しか許されない」という非常に高い水準です。
・エレクトロニクス、医療機器業界
半導体や医療機器など、信頼性が重視される分野でも同様に厳しい基準が存在します。場合によっては「1PPM以下」などの要求が課せられることもあります。
社内での目標設定のポイント
・過去の実績やトレンドを考慮して現実的なラインを設定する
・ロットごとのばらつきを考慮し、月単位・四半期単位で管理する
・CpkやPpkなどの工程能力と合わせて評価する
PPMを用いた品質改善アプローチ
・不良発生の「見える化」
PPMの活用により、不良の発生傾向を数値として「見える化」することが可能になります。
日・週・月単位で推移を記録することで、突発的な異常だけでなく、じわじわと悪化していく慢性的な品質問題も早期に察知できます。
数値が示す変化に気づくことが、初期流動管理や再発防止への第一歩となります。
・管理図との連携
PPMの推移を管理図(X̄-R管理図や折れ線グラフなど)に組み込むことで、定量的な品質管理が可能になります。
たとえば、統計的な異常値を自動検出しやすくなり、設備異常や工程ズレの早期発見につながります。
管理図と併用することで、PPMが単なる数値報告ではなく、異常の兆候をつかむツールとして機能します。
・改善へのフィードバック
目標PPMを上回る結果が出た場合には、なぜ不良が発生したのかを振り返り、原因分析を行うことが重要です。
たとえば、不良モード別にパレート図を作成したり、なぜなぜ分析やFMEAを用いて再発防止策を検討したりすることで、次回以降のPPM改善へとつながります。
このサイクルを定着させることで、品質改善が持続的に回る仕組みを構築できます。
PPMと工程能力指数(Cpk, Ppk)の関係性
PPMと工程能力指数(Cp, Cpk, Pp, Ppk)は密接に関係していますが、まったく同じものではありません。
・Cpkが高くてもPPMが高い場合がある
Cpkはあくまで正規分布に基づいた理論上の能力値であるため、工程に突発的な異常やシフトがある場合、実際のPPMは悪化することがあります。
・PPM=理論的不良率ではない
理論上のCpkから予測できるPPM値はあくまで理想値です。現場では実測値としてのPPMと理論値を比較し、ズレの有無=実力と理論のギャップを見極めることが重要です。
まとめ:PPMは「現場の品質スコア」である
PPMは、製造現場の品質レベルを数値で客観的に示すスコアです。
製品の不良発生状況を100万個あたりの件数で表すことで、他部署・他社・他工程との比較がしやすく、品質の良し悪しを明確に伝えることができます。
このスコアが良ければ「品質が安定している」と判断できますし、悪化すれば「何らかの異常や管理の緩みがある」というサインになります。
また、工程能力指数(CpkやPpk)が工程の“ポテンシャル”を示すのに対し、PPMは“実際の成果”を示す指標です。この2つを組み合わせることで、現場の真の品質状態が見えてきます。
PPMは品質改善の出発点であり、継続的な管理と対策の判断材料にもなります。現場の品質スコアとして、日々のチェックと改善活動にしっかりと組み込んでいきましょう。


